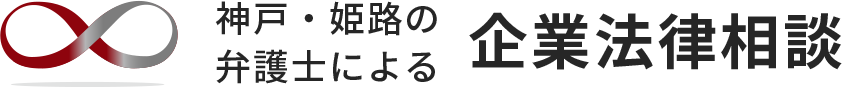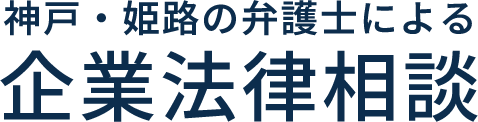おとり広告(景品表示法)の法的注意点

おとり広告とは
おとり広告とは、「実際には購入できない商品等であるのに、一般消費者が購入できるかのように誤認させるおそれがある表示」をいい、景品表示法の不当表示として規制されていいます。このような表示は、広告された商品が購入できるかのように不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する行為であることが明らかであることから、これを不当表示として規制するものです。
広告した商品とは別の商品を売りつけることだけでなく、広告した商品について適切な販売数量を用意していない場合にも、おとり広告規制に違反するリスクがありますので、ご注意ください。
おとり広告告示・運用基準
おとり広告を的確に規制できるようにするため、景品表示法5条3号に基づき、「おとり広告に関する表示」(以下「おとり広告告示」といいます。/平成5年公取委告示第17号)が、以下の各号に掲げるとおり不当表示として定められています。
また、運用基準として、『「おとり広告に関する表示」等の運用基準(平成5年4月28日公取委事務局長通達第6号)』(以下「運用基準」といいます。)が定められており、おとり広告告示の解釈が示されています。
【おとり広告告示1号】
「取引の申出に係る商品又は役務について、取引を行うための準備がなされていない場合その他実際には取引に応じることができない場合のその商品又は役務についての表示」
表示された商品又は役務が実際には提供されない場合を意味しており、おとり広告の典型といえるものです。「取引を行うための準備がなされていない場合」として、次のようなものが例示されています(運用基準第2,1-(1))。
㋐ 当該店舗において通常は店舗展示販売されている商品について、広告商品が店頭に陳列されていない場合
㋑ 引渡しに期間を要する商品について、広告商品については当該店舗における通常の引渡期間よりも長期を要する場合
㋒ 広告、ビラ等に販売数量が表示されている場合であって、その全部又は一部について取引に応じることができない場合
㋓ 広告、ビラ等において写真等により表示した品揃えの全部又は一部について取引に応じることができない場合
㋔ 単一の事業者が同一の広告、ビラ等においてその事業者の複数の店舗で販売する旨を申し出る場合であって、当該広告、ビラ等に掲載された店舗の一部に広告商品等を取り扱わない店舗がある場合
このように、引渡に時間がかかる場合や一部の商品しか準備ができてない場合も、「取引を行うための準備がなされていない場合」に該当することにご注意ください。
【おとり広告告示2号】
「取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示」
ここでいう供給量が「著しく限定されている」場合とは、広告商品等の販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合をいいます(運用基準第2,2-(1))。また、限定の内容が「明瞭に記載されていない」場合とは、実際の販売数量が当該広告、ビラ等に商品名等を特定した上で明瞭に記載されていなければならず、たとえば「売り切れ御免」といった表示等、販売数量が限定されている旨のみが記載されているだけでは、限定の内容が明瞭に記載されているとはいえません(運用基準第2,2-(2))。
【おとり広告表示3号】
「取引の申出に係る商品又は役務の供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明瞭に記載されていない場合のその商品又は役務についての表示」
供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量の限定については、実際の販売日、販売時間等の販売期間、販売の相手方又は顧客一人当たりの販売数量が当該広告、ビラ等に明瞭に記載されていなければならず、これらについて限定されている旨のみが記載されているだけでは、限定の内容が明瞭に記載されているとはいえません(運用基準第2,3)。
【おとり広告告示4号】
「取引の申出に係る商品又は役務について、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品又は役務についての表示」
運用基準には、「取引の成立を妨げる行為が行われる場合」に当たる場合が、次のとおり例示されています(運用基準第2,4-(1))。
●広告商品を顧客に対して見せない、又は広告、ビラ等に表示した役務の内容を顧客に説明することを拒む場合
●広告商品等に関する難点をことさら指摘する場合
●広告商品等の取引を事実上拒否する場合
●広告商品等の購入を希望する顧客に対し当該商品等に替えて他の商品等の購入を推奨する場合において、顧客が推奨された他の商品等を購入する意思がないと表明したにもかかわらず、重ねて推奨する場合
●広告商品等の取引に応じたことにより販売員等が不利益な取扱いを受けることとされている事情の下において他の商品を推奨する場合
また、「合理的理由」とは、未成年者に酒類を販売しない等広告商品等を販売しないことがあげられます(運用基準第2,4-(2))。
違反事例
おとり広告は様々な業界でみられますが、特に不動産取引において問題とされることが多いです。昭和55年に「不動産のおとり広告に関する表示」(昭和55年4月12日公取委告示第14号)が定められており、不動産取引におけるおとり広告については、この告示が適用されることになります。
その他の違反事例としては、中古自動車やミシン等の耐久財的な商品や、ブランド食品(うなぎ、牛肉等)、ガス機器、通信端末を対象としたものがあります。記憶に新しいところでは、回転寿司チェーンの期間限定の寿司に対して、措置命令が行われた事例があります。
かつては、不動産や中古自動車といった特定物の販売を適用対象としていましたが、最近の実務運用の特徴としては、特定物ではない商品について、広告された商品が準備されていなかったことに対して、おとり広告として措置命令を出す傾向にあるといわれています。
対応策
上記のとおり、イチオシ商品や特売品を使って集客しようとすることには、景品表示法上の法的リスクがあります。そのような広告をしようとする場合、まずは販売可能な数量をご確認いただき、数量が限られている場合には、その旨を消費者に分かりやすいように広告に表示することを心がけてください。
広告の法的対応にお悩みの場合は、法律事務所瀬合パートナーズに是非ご相談ください。
※ 上記記事は、令和4年6月13日時点での情報となります。
関連記事
広告記事
-
広告
Q.企業向けの販売セミナーをしたいと考えています。セミナー参加者全員に,参加特典として自社商品をお渡ししようと思うのですが,問題ないでしょうか。
-
広告
Q.化粧品の広告規制について
-
広告
広告における打消し表示
-
広告
広告における二重価格表示
-
広告
広告における不当表示
-
広告
景品規制における法的留意点
-
広告
景品類の認定と取引付随性
-
広告
景表法における景品類の認定と取引付随性について
-
広告
景表法で規制される「有利誤認表示」とは
-
広告
ステルスマーケティング規制の概要(令和5年10月1日施行)
-
広告
景品表示法における管理措置指針の概要と社内体制整備について
-
広告
No.1表示を行う際の景表法上の留意点
-
広告
令和5年景品表示法改正の概要
-
広告
コンプガチャの禁止とその対策
-
広告
ライブイベントやコンサートの座席に関する不当表示とその予防策