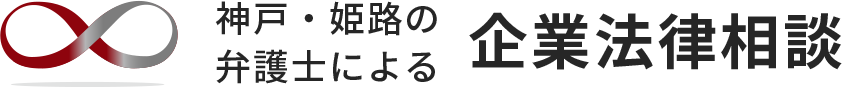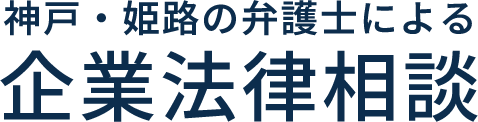景品表示法の概要(不当景品類及び不当表示防止法)

景品表示法とは
景品表示法
近時、健康食品や美容エステをはじめ、広告の行き過ぎた表現について、消費者庁など関係当局が厳しい対応をとるようになってきています。そこで、景品表示法について、概略を説明をさせていただきます。
景品表示法は、消費者の選択を誤らせるような不当な表示や過大な景品類の提供を制限しまたは禁止することで、消費者の利益を保護することを目的に作られた法律であり、基本的には行政処分を定めるものです。かつて、独占禁止法の特例法として、公正な競争を確保し、一般消費者の利益を保護することを目的とし、公正取引委員会が所管していましたが、一般消費者の利益を保護するものとして、消費者庁に移管されました。
不当表示の3類型
景品表示法の規制する不当表示には、次の3類型が定められています。
① 優良誤認表示(景品表示法5条1号)
商品・サービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示や、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示をいいます。健康食品や美容エステ等の関係でよく問題とされます。
後記2のとおり「不実証広告規制」(景品表示法7条2項)と呼ばれる制度があり、特に注意が必要です。
② 有利誤認表示(景品表示法5条2号)
商品・サービスの価額その他取引条件について、一般消費者に、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示や、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示をいいます。
不当な二重価額表示などで問題となることがあります。
③ その他告示で指定する表示(景品表示法5条3号)
その他、内閣総理大臣が指定する以下のものについても「不当表示」と定めその表示を禁止しています。
◆ 無果汁の清涼飲料水等についての表示
◆ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
◆ 不動産のおとり広告に関する表示
◆ おとり広告に関する表示
◆ 有料老人ホームに関する不当な表示
◆ 商品の原産国に関する不当な表示
食品の場合、食品表示法とともに原産国の表示についても配慮する必要があります。
景品表示法違反の効果
景品表示法の規制する上記不当表示に違反すると、消費者庁や都道府県から措置命令(表示の中止等)が出されたり、場合によっては後記3の課徴金納付命令が出されることがあります。また、消費者庁の認証を受けた適格消費者団体による差止請求の対象ともなります(景品表示法30条)。
公正競争規約
事業者団体などで策定する「協定又は規約」(景品表示法31条。いわゆる公正競争規約)がある場合、団体の加盟事業者は、この規約の内容も遵守する必要がありますので、ご注意ください。なお、公正競争規約については、公正取引委員会の認可を受ける必要があります。
不実証広告規制
上記1(2)①の優良誤認表示に該当するおそれがある場合、不実証広告規制(フジツショウコウコクキセイ)と呼ばれる制度があります。
この制度は、消費者庁が、商品等の内容(効果、性能)に関する表示が、優良誤認表示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、事業者に対し、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、もし事業者が資料を提出しない場合や、提出資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、対象となる表示は、不当表示とみなされるものです。なお、課徴金との関係では推定となります(景品表示法8条3項)。
資料の提出期間も15日間と短く、また裏付けと認められる基準もかなり厳しいものです。したがって、事業者としては、表示の裏付け資料を事前に準備しておくことをお勧めします。
裏付けと認められる基準については、消費者庁から出されている「不当景品類及び不当表示防止
法第7条第2項の運用指針」(不実証広告ガイドライン)をご参照ください。
課徴金制度の導入
平成28年4月1日から、景品表示法違反の不当表示(①優良誤認と②有利誤認のみ)に対して、課徴金の納付を命令する制度が導入されました(景品表示法8条~)。この制度は、命令の対象となった事業者が、対象行為による商品等の売上額の3%の金額を、課徴金として国に支払わなければならないものです。
もっとも、課徴金の金額が150万円未満である場合や、不当表示であることにつき事業者が相当の注意を怠った者ではないと認められる場合などにおいては、課徴金納付を命ずることはできないとされています。
その他の広告・表示規制
広告・表示については、景品表示法のほかにも、消費者契約法や特定商取引法等の消費者保護法、食品表示法や健康増進法等の食品表示関連法、宅建業法や旅行業法、医療法、薬機法等の各種業法による規制に抵触しないか検討する必要があります。その他にも、不正競争防止法の偽装表示規制、民事上の詐欺、錯誤、瑕疵担保責任や刑事上の詐欺罪等も関連します。
なお、近時、最高裁の平成29年1月24日判決が、クロレラ関連の健康食品の新聞チラシ広告に関する事案で、消費者契約法等で規定されている「勧誘をするに際し」の要件(不実告知行為等)について、「不特定多数の消費者に働きかけを行う場合を一律に除外することは相当ではなく、具体的な記載内容によっては、広告も『勧誘』に当たる場合がある」との判断が出されました。
上記判断は、新聞チラシ広告以外の一般的な広告(ネット通販上の広告も含む)にも適用されるものであり、契約の取り消しの可否に直結するものですので、特に注意が必要です。
まとめ
冒頭のとおり、近時、健康食品や美容エステをはじめ、広告の行き過ぎた表現について、消費者庁など関係当局が厳しい対応をとるようになってきており、景品表示法違反として取り上げられることも多くなっています。景品表示法違反となると、措置命令や課徴金命令や刑罰といったリスクだけでなく、信用問題にも発展しかねません。
事業者としては、広告表現について安易に考えるのではなく、慎重な対応と根拠となる資料の事
前準備が必要となります。景品表示法をはじめその他の広告問題に関してお悩みの経営者の方は、この問題に詳しい弁護士にご相談ください。
関連記事
広告記事
-
広告
Q.企業向けの販売セミナーをしたいと考えています。セミナー参加者全員に,参加特典として自社商品をお渡ししようと思うのですが,問題ないでしょうか。
-
広告
Q.化粧品の広告規制について
-
広告
おとり広告(景品表示法)の法的注意点
-
広告
広告における打消し表示
-
広告
広告における二重価格表示
-
広告
広告における不当表示
-
広告
景品規制における法的留意点
-
広告
景品類の認定と取引付随性
-
広告
景表法における景品類の認定と取引付随性について
-
広告
景表法で規制される「有利誤認表示」とは
-
広告
ステルスマーケティング規制の概要(令和5年10月1日施行)
-
広告
景品表示法における管理措置指針の概要と社内体制整備について
-
広告
No.1表示を行う際の景表法上の留意点
-
広告
令和5年景品表示法改正の概要
-
広告
コンプガチャの禁止とその対策