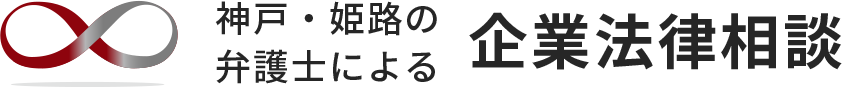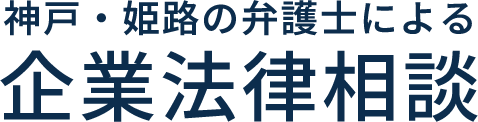役員報酬制度における信託(株式交付信託・信託型ストックオプション)の有効活用
第1 役員報酬規制とコーポレートガバナンス
会社法は、お手盛り防止を目的とした各種役員報酬規制を設けています(会社法361条1項、404条3項)。しかしながら、近時は、むしろ取締役に対する動機付けとして、積極的に機能すべきであるという考え方が有力に主張されるようになってきました。特に、コーポレートガバナンス・コードにおいても、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして報酬が機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬や、自社株報酬の導入を促進すべきこととされています(原則4-2、補充原則4-2①)。
そこで、このようなインセンティブ報酬の一つとして、株式または新株予約権を取締役に与えることがあります(エクイティ報酬)。しかしながら、株式そのものを直接に付与する制度は、第2記載のとおり、現行の会社法において、いくつか問題点があります。
そこで、信託が有効な解決策となり得るのです。具体的には、『株式交付(給付)信託(以下、「株式交付信託」で統一する)』、『信託型ストックオプション(新株予約権)(以下、「信託型ストックオプション」で統一する)』が利用されています。
これらの信託の利用方法が、企業の持続的な成長に向けた健全なインセンティブ報酬として、どのように有効な解決策となるのか、他の制度である『特定譲渡制限付株式』も例にとり、その長短を比較しながら、以下、説明します。
第2 株式そのものを直接に付与する制度の問題点
会社が取締役に報酬として株式そのものを直接に付与することは、現行の会社法上、次のような問題点があります。
①無償発行の問題
募集株式の発行は、募集新株予約権の発行の場合(会社法238条1項2号)とは
異なり、無償で行うことができない規定の仕方になっています(会社法199条1項2号)。また、株式無償割当ての制度は払込みを要しませんが(会社法185条)、既存の株式数に応じた割当てが必要になるため(会社法186条2項)、実質的には株式分割にほぼ等しく、報酬として利用することはできません。
②労務出資の問題
通説は、株式について労務出資は認められないと解されていますので、金銭での払込みに代えて労務による出資という構成をとることもできません。
そこで、第3記載のとおり、信託を利用することにより、これらの問題点をクリアすることが可能となります。
第3 各エクイティ報酬の内容と長短
1 株式交付信託
(1)内容
株式交付信託とは、主に次のような仕組みです。
①会社が株主総会決議(会社法361条)により決定した金額を上限に金銭を拠出し、受託者となるべき者との間で、当該金銭を信託財産とする信託契約を締結する。
②受託者は、信託契約に基づき、市場または会社を通じて当該金銭を原資として株式を先行取得する。
③受託者が受益者たる取締役に対して一定の方式で算出される数の株式を一定の場合に交付する。
④信託期間中の業績目標の未達成などにより信託終了時に株式が残存した場合には、受託者は残余の株式を会社に無償譲渡する等の措置をとる。
なお、上場会社の株式報酬の実務では、会社が直接、取締役に対して株式を交付する代わりに、会社は金銭を拠出して信託を設定し、受託者である信託銀行が、当該金銭を原資として会社から株式の交付を受けるかまたは市場で株式を購入し、その株式を、予め会社が定めたスキームに従って取締役に交付するという形をとることが多いです。
(2)長所
株式交付信託は、会社が取締役に直接に株式を交付するわけではないので、上記第2記載の①無償発行の問題、および②労務出資の問題が回避できます。
また、始めに株式をまとめて信託に割り当てることで、その時点での交付条件を冷凍保存できます(タイムカプセル機能)。そのため、業績への貢献度や相性が不明な役員について、採用時に割当先を決めずに、後決めが可能となります。また、役員を採用するたびに発行する必要がないので、煩雑な手続やコスト増を避けることができます。
(3)短所
受託者による株式の取得は、会社の拠出した金銭を財源とします。そのため、会社の計算による取得であって、自己株式の取得規制(会社法155条等)が及ぶのではないか、有効な払込みとはいえないのではないか、といった懸念が生じます。
そこで、信託財産に属する株式として議決権を行使しないこととする等、会社の計算による取得とはみられないようにするための工夫が必要とします。
また、株式交付信託は、会社法361条1項各号のうち、いずれの報酬に該当するのかが明らかではない等、法的に不安定な面もあります。
なお、信託銀行等を利用して、株式交付信託を発行する場合、信託会社に対して、高額の手数料を支払う必要があり、委託者の経済的負担が大きいです。
2 信託型新株予約権(ストックオプション)
(1)内容
信託型ストックオプションとは、有償ストックオプションの一種であり、信託を利用した報酬制度である。主に次のような仕組みです。
①委託者から受託者に対し、ストックオプションの時価相当の現金(発行価格)を払い込む。
②受託者から発行会社に対し、委託者から払い込みを受けた①の発行価格を払い込む。
③発行会社は、受託者から払い込みを受けた金額に相当するストックオプションを割り当てる。
④受託者がストックオプションを保管している間、受益者には発行会社からストックオプションに将来交換できるポイントを割り当てていく。
⑤受託者が預かる信託の保管期間が満了した際(上場や事業売却など予め任意に設定可)、信託内のストックオプションが、受益が持っているポイント数に応じて役員や従業員に割り振られる。
(2)長所
信託型ストックオプションも、会社が取締役に直接に株式を交付するわけではないので、上記第2記載の①無償発行の問題、および②労務出資の問題が回避できます。
始めにストックオプションをまとめて信託に割り当てることで、その時点でのストックオプションの条件(行使価格等)を冷凍保存できます(タイムカプセル機能)。
そのため、業績への貢献度や相性が不明な役員について、採用時に割当先を決めずに、後決めが可能となります。また、役員を採用するたびに発行する必要がないので、煩雑な手続やコスト増を避けることができます。
(3)短所
株価が企業業績以外の事情により下落しているときに、業績連動型報酬としての機能を発揮できません(この点、株式交付信託では、企業業績に関係なく株価が下落している局面においても、一定のインセンティブを役員に付与することができます)。
また、信託型ストップオプションは、従前、付与を受ける役職員に対して、株式譲渡時の譲渡所得のみが発生するとの想定のもとで利用されてきました。
しかしながら、近時、国税庁は、信託型ストックオプションについて、従前とは異なる見解を公表しました。
具体的には、信託会社がストックオプションの付与を受ける時点及び役職員がストックオプション交付を受ける時点においては、課税が発生しないことを肯定したうえで、「役職員が当該ストックオプションを行使して発行会社の株式を取得した場合、その経済的利益は、給与所得なります(所得税法28条、36条②、所令84③)」と回答し、ストックオプションの行使時点において、その行使時の株式の時価とストックオプションの発行時の支払額及び行使価格の合計額との差額について給与所得として課税されるとの見解を示しました。その理由として、「実質的には、会社が役職員にストックオプションを付与していること、役職員に金銭等の負担がないこと」をあげています。
国税局の上記見解に対して、訴訟を検討している企業が複数社あるとの報道もあります。このように、信託型ストックオプションの課税関係は現在もなお不安定です。
なお、信託銀行等を利用して、ストックオプションを発行する場合、信託会社に対して、高額の手数料を支払う必要があり、委託者の経済的負担が大きいです。
3 特定譲渡制限付株式
(1)内容
ア.特定譲渡制限付株式の仕組み
主に次のような仕組みをとります。
(ア)会社が株式総会決議に基づき取締役に金銭報酬を付与することとする(会社法361条)。
(イ)これによって取締役が取得した金銭報酬債権を現物出資し、会社が譲渡制限を付した株式を取締役に新株発行または自己株式処分の方法で交付する。
イ.譲渡制限の定め方
次の2つの方法がある。
(ウ)種類株式として譲渡制限株式を利用し、一定期間の経過や業績の達成を条件に譲渡制限を消滅させる(または普通株式に転換できる旨の取得条項や取得請求権を定めておく)方法
(エ)会社と取締役との間の合意で譲渡制限を定める方法
(2)長所
上記(1)のとおり、取締役は、会社から株式の交付を受ける対価として金銭報酬債権を現物出資するという構成をとるので、上記第2記載の①無償発行の問題、および②労務出資の問題が回避できます。
なお、平成28年税制改正により、会社が取締役らに特定譲渡制限付株式を交付した場合、当該取締役らは、交付時点ではなく譲渡制限の解除時点で所得税が課せられ、会社側は、一定の要件のもとで、譲渡制限の解除時点の属する事業年度において、役務提供に係る費用の額を損金算入することができるようになりました(所得税法施行令84条1項、法人税54条1項、法人税法施行令111条の2第1項等)。
(3)短所
(ウ)譲渡制限の定めを種類株式によって実現しようとすると、株式の付与ののちに会社が定款変更等をしようとするたびに種類株主総会決議が必要となる場合が生じ(会社法322条)、実務上の負担を生じさせるという問題があります。
また、会社法上の譲渡制限株式の制度は、譲渡の相手方を制限するだけの制度であり、会社が譲渡を承認しない場合であっても、譲渡人は会社または指定買取人に株式を譲渡することができます(会社法140条1項、4項参照)。そのため、中長期のインセンティブを付与する目的に合致しないおそれがあります。
さらに、(エ)契約による譲渡制限は、それに違反して第三者に株式が譲渡されたときも、譲渡自体は有効であり、譲渡制限の実効性をどのように確保するかが問題となります。
第3 まとめ
上記のとおり、信託制度(株式交付信託、信託型ストックオプション)は、会社が取締役に報酬として株式そのものを直接に付与する制度と比べて、①無償発行の問題、②労務出資の問題をクリアできる点で、有効な解決策となります。また、いずれもタイムカプセル機能がある点で利便性が高いといえます。なお、特定譲渡制限付株式は、信託制度を利用する場合に比べて、その実効性に懸念があります。
個人的には、上記信託制度のうち、課税関係で不安が残る信託型ストックオプションより、株式交付信託を利用する方がよいと考えます。
なお、令和元年の会社法改正により、上場会社が株式そのものを報酬として付与することのできる制度が新設され(同法202条の2・361条1項3号)、また、株式と引換えに行う払込みに充てるための金銭を報酬として付与する場合について、規定が整備されています(会社法361条1項5号イ)。そのため、上場会社においては、会社が取締役に報酬として株式そのものを直接に付与する方法も、利用し易くなってきていると考えられます。
【主な参考文献】
・田中亘著「会社法(第4版)」東京大学出版会 266頁から273頁
・江頭憲治郎著「会社法(第9版)」有斐閣 471頁から489頁
・北村雅史著「会社法実務問答集Ⅴ」商事法務 38頁から40頁、278頁から283頁
・西村あさひ法律事務所著「ストックオプション税制に関する新しい動き―いわゆる信託型ストックオプションへの課税関係を中心に―」)2023年6月29日号
会社法・金融商品取引法記事
-
会社法・金融商品取引法
ハイブリッド型バーチャル株主総会の概要
-
会社法・金融商品取引法
Q.友好的資本提携とはどのような提携を意味しているのでしょうか?
-
会社法・金融商品取引法
Q.招集通知発送後に株主総会の開催日時・場所を変更することはできるか?
-
会社法・金融商品取引法
会社の代表取締役が認知症になってしまった場合
-
会社法・金融商品取引法
代表取締役・取締役の退任について
-
会社法・金融商品取引法
取締役(役員)を解任する際の注意点と損害賠償リスクを回避する方法
-
会社法・金融商品取引法
創業株主間契約の重要性
-
会社法・金融商品取引法
資本政策の重要性
-
会社法・金融商品取引法
代表取締役の変更と特別利害関係人
-
会社法・金融商品取引法
役員(取締役・監査役・執行役員等)に対する処分と対応方法
-
会社法・金融商品取引法
取締役会と会社法規定について
-
会社法・金融商品取引法
代表取締役の解任について
-
会社法・金融商品取引法
取締役の紛争
-
会社法・金融商品取引法
取締役の責任(競業避止義務)
-
会社法・金融商品取引法
取締役の責任(利益相反について)