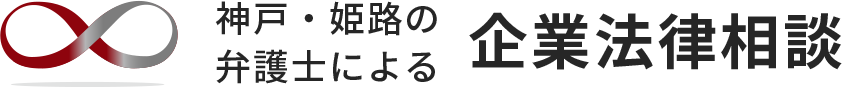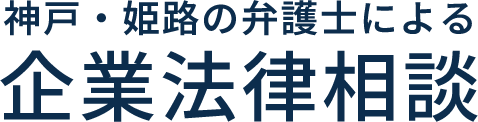親族外承継を成功させるためのポイントと弁護士の役割
1.親族外承継とは
親族外承継の定義と概要
親族外承継とは、文字どおり経営者の親族ではない第三者に事業を引き継ぐ形態のことを指します。多くの中小企業では、これまで親族(子どもや配偶者、兄弟姉妹など)が後継者となる「親族内承継」が一般的でした。しかし、少子化の影響や、事業承継への意欲や能力を持つ親族がいないケースが増えたことなどにより、親族外の社員や経営者候補、あるいは他企業・投資ファンドなどに事業を引き継ぐケースが増加しています。
親族内承継やM&Aとの違い
• 親族内承継
親族内承継は、現経営者の親族に後継者がいる場合に選択されることが多い形態です。家族間での信頼関係が築きやすい一方、親族内でも事業に対する意欲や能力が合わなければスムーズに承継が進まないこともあります。
• M&A
M&A(合併・買収)は、一般に外部の企業や投資家が株式や事業を取得して経営権を得る形態です。M&Aでは買い手となる企業や投資家が株式の大半を取得し、大幅に経営方針が変わる可能性も高い点が特徴です。一方、親族外承継の場合でも、実質的にはM&Aと近しい手法が採用されることがありますが、最終的には「経営権を誰に、どのような形で渡すか」に違いが現れます。
2.親族外承継のメリット
➀後継者の選択肢が広がる
親族外承継のメリットは、後継者の選択肢が広がることです。親族に経営意欲や能力が不足している場合でも、社内外の優秀な人材や外部の企業・ファンドなど、幅広い候補から後継者を探すことができます。特に中小企業の場合、「引き継ぎ先さえ見つかれば事業は継続したい」という経営者の希望が強いケースが多く、親族外承継という選択肢は事業存続のために重要な意味を持ちます。
➁企業文化や経営方針の維持
M&Aによる買収の場合、買い手企業の方針に合わせて組織改革が行われ、企業文化が大きく変わるリスクもあります。一方、親族外承継でも承継先が全く異なる企業や投資家になる場合はありますが、「会社の理念や文化を尊重した上で経営を続ける」という条件を付けることができるケースもあります。また、既存の従業員が引き継ぐMBOやEBOであれば、これまでの経営方針や社風を維持しやすいのも利点です。
3.親族外承継のデメリットと課題
➀株式や資産の承継方法
親族外承継の場合、現経営者が保有する株式や資産をどのように譲渡・承継するのかが大きな課題となります。たとえば、社内外の個人に引き継ぐ場合は株式譲渡になるのか、従業員が引き受けるならば従業員買収(EBO)に該当するのか、外部ファンドから資金を調達して買い取るのかなど、法的・税務的な検討が必要となります。
➁経営者保証の引き継ぎ問題
中小企業の多くは融資を受ける際に経営者自身が連帯保証をしているケースが一般的です。親族内承継でも問題にはなりますが、親族外承継では後継者が経営者保証を引き継ぎたがらないケースもあります。後継者候補が見つかっても、金融機関との交渉を含めて保証の扱いをどうするかが大きなハードルとなりがちです。
4.親族外承継の具体的な方法
MBO(マネジメント・バイアウト)やEBO(従業員買収)の活用
• MBO(マネジメント・バイアウト)
現在の経営陣(役員クラスなど)に株式を買い取ってもらい、経営を引き継ぐ方法です。現場をよく理解している経営陣が後継者になるため、社内の混乱が少なく、スムーズに事業を継続できるメリットがあります。
ただし、経営陣が株式を取得するために必要な資金をどのように調達するか、金融機関の融資をどの程度受けられるかなど、事前の準備・交渉が不可欠です。
• EBO(従業員買収)
従業員が中心となって事業を買い取り、経営を継承する形態です。従業員は会社の業務内容や顧客との関係性を熟知しているため、外部から引き継ぐよりもリスクが少なく、従業員のモチベーション向上にもつながるケースがあります。
ただし、EBOもMBO同様、従業員サイドで株式買収資金をどのように準備するかが大きな課題となります。
これらの手法以外にも、外部投資家やファンドを活用して事業承継を進める方法などがありますが、いずれにしても「承継に必要な株式譲渡や資金調達をどのように行うか」が最初の大きな検討ポイントです。
5.親族外承継を成功させるためのポイント
➀早期の後継者選定と育成
親族外承継を検討する場合、まずは可能性のある後継者候補を早期に見つけ、十分な時間をかけて育成・準備することが重要です。経営者が高齢になり、引退を目前にして初めて探し始めると、候補者との交渉や社内外への説明に時間がかかり、スムーズに進みにくくなります。早い段階から承継の必要性を見据え、人材育成や企業価値向上のための取り組みを進めておきましょう。
➁関係者への十分な説明と理解の獲得
社内の従業員はもちろん、取引先や金融機関などに対しても、親族外承継の意図やメリットをしっかりと説明し、理解を得ることが大切です。特に経営者保証や既存取引条件の継続など、ステークホルダーが関心を持つポイントについては、可能な限り透明性を高めて協議を行う必要があります。
後継者候補とともに説明会を開催する、経営計画書やビジョンを共有するといった工夫を行い、社内外の不安を解消していくことが成功の鍵となります。
6.弁護士の役割と重要性
➀法的課題の解決と契約書の作成
親族外承継には、株式譲渡契約や合意書の作成、労務管理の再調整、役員変更に伴う定款の修正など、多岐にわたる法的手続きが絡みます。特に以下のような場面で弁護士のサポートが役立ちます。
• 株式譲渡契約・事業譲渡契約の作成・確認
株式を譲渡する場合の条件やスケジュール、価格設定などを明確に取り決める必要があります。また、秘密保持条項や競業避止義務なども考慮した包括的な契約書の作成が望まれます。
• 金融機関との交渉支援
経営者保証の解除や融資条件の再設定など、金融機関との交渉は法的根拠を踏まえた慎重な話し合いが必要です。弁護士が同席・助言することで、交渉をスムーズに進められるケースが多くあります。
• 労務・人事面の整備
後継者が変わることによって、就業規則や役員報酬、従業員の雇用条件などを見直す必要が出てくる場合があります。これらも労働法規を踏まえた適切な手続きが欠かせません。
➁税務対策や資金調達のサポート
弁護士だけでなく、公認会計士や税理士など、専門家と連携した総合的なサポートが必要です。特に株式評価や企業価値算定、売却益や譲渡益にかかる税金など、事前に最適化を図ることで、承継後の経営を安定させることに役立ちます。弁護士はこうした専門家と連携しながら、法的観点からリスクヘッジを行う重要な役割を果たします。
7.親族外承継の典型事例の紹介
成功事例:専門性を活かして従業員が承継
ある製造業の中小企業では、先代社長に子どもがおらず、従業員も比較的若い人材が揃っていました。社長は早期から「経営幹部の中から後継者を育てる」方針を示し、数年をかけてMBOの準備を進めました。結果的に、専務や部長クラスが出資者となり、金融機関の支援も取り付けて経営権を取得。外部から新たな経営陣を呼ぶ必要がなく、企業文化や取引関係も大きく変わることなく承継に成功しています。
• 早い段階からの後継者育成
• 金融機関・専門家との連携
• 社員のモチベーション維持
失敗事例:外部投資家との方針不一致
一方、別の事例では、IT系中小企業の社長が後継者不在に悩み、外部の投資ファンドへ株式を譲渡しました。当初は「現場の意向を尊重する」との約束がありましたが、事業拡大に向けた投資やリストラなど、投資家側の方針と従業員側の考えとの間に温度差が生じ、最終的に多くの有力社員が退職してしまいました。
• 投資家との契約内容(企業文化の維持や経営方針)を曖昧にしない
• 承継後の具体的な経営プランに関する合意形成
8.まとめ
親族外承継は、事業を持続的に発展させるための有力な選択肢の一つですが、その一方で親族内承継やM&Aとは異なる課題やリスクが存在します。成功のカギとなるのは、①早期の準備と後継者育成、②株式や資産、経営者保証などの整理、③ステークホルダーへの十分な説明と協力体制の確立、④専門家(弁護士・税理士・会計士など)との連携です。
弁護士は、契約書作成や法的交渉、税務・財務専門家との連携など、親族外承継を円滑に進めるために欠かせないパートナーとなります。これから事業承継を考える経営者の方は、ぜひ早い段階から弁護士を含む専門家に相談し、最適な方法を探ってみてください。
事業承継M&A記事
-
事業承継M&A
M&Aで弁護士が担う役割と弁護士に依頼するメリット
-
事業承継M&A
M&Aに関するよくあるご相談
-
事業承継M&A
支配株主による少数株式の集約方法(スクイーズ・アウトなど)
-
事業承継M&A
譲渡制限株式の買取請求制度における注意点
-
事業承継M&A
ジョイントベンチャー契約(合弁契約/JV契約)
-
事業承継M&A
表明保証条項
-
事業承継M&A
事業承継
-
事業承継M&A
親族内承継を成功させるための弁護士活用法
-
事業承継M&A
事業譲渡
-
事業承継M&A
法務DD(デューデリジェンス)とは~M&Aに失敗しないために~
-
事業承継M&A
弁護士が解説する人権デュー・デリジェンスの概要とポイントについて
-
事業承継M&A
スクイーズアウト
-
事業承継M&A
事業承継のための株式譲渡を受ける際の注意点
-
事業承継M&A
Change of control条項について
-
事業承継M&A
再生・倒産・M&A