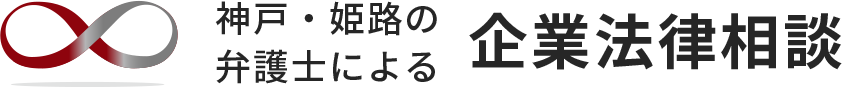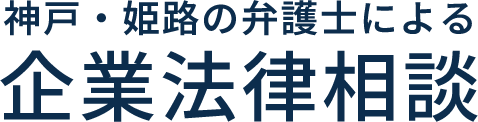相談・解決事例
Case42 従業員の死亡退職金の支払い方法について助言した事例
業 種 運送業
お困りの問題 人事労務
相談内容
従業員が死亡した際の退職金(死亡退職金)について、誰に支払えばよいか分からないということで、ご相談がありました。状況としては以下の通りです。
・退職金規定自体はあるが、受給権者の定めはない
・当該従業員の家族としては、配偶者と母だけである(配偶者との間に子はいない)
弁護士の助言・対応
まず、死亡退職金の法的な取扱いについて、以下の通りご説明しました。
・退職金規定等に受給権者の範囲や順位が定められていない場合、原則的に、相続財産として扱われることになる。そのため、当該社員の法定相続人に支払うことになる。
・今回の場合、法定相続人は配偶者と母の2名となり、法定相続分の割合は、配偶者が3分の2、母が3分の1となる。
次に、上記を前提に、実務上の対応方法について以下の通りご助言いたしました。
・対応方法としては、次の3パターンが考えられる。
①配偶者と母それぞれに対して、法定相続分に応じた額を支払う
②特定の者を相続人代表者として、まとめて支払う(二人の中で清算してもらう)
③遺産分割協議が成立するまで支払を保留する
・今回の場合、配偶者と母が同居しているため、比較的連絡もつきやすいものと考えられる。双方と連絡がつく場合には、①の方法でよい。
・もしくは、窓口を一本化するという意味では、②も簡便な方法ではある。ただし、例えば、配偶者に全額支払う場合、後に母から会社側にクレームがこないよう、配偶者に全額支払うことについて、母から同意書をとる必要があるため、注意が必要。
最後に、今後の規定の見直しに向けて、以下の通りご助言いたしました。
・退職金規定等で受給権者を定めていない場合、相続財産をめぐる親族間のトラブルに会社が巻き込まれるおそれがあるため、受給権者に関する定めを新たに設けて、受給権者の範囲と順位を明確にしておく方が合理的である。
・実務上は、労働者が業務上死亡したときの遺族補償を受ける遺族の範囲を定めた労基法施行規則42条から45条までの規定を準用した定めを置く例が多く(配偶者が第一順位、次に生計を一にしていた子、父母、孫、祖父母の順)、特にこだわりがない場合には、この例にならう形でよいと思う。
相談・解決事例
-
Case41 システム開発業務の委託に係る取引基本契約のリーガルチェック
-
Case40.建物解体工事による損害について賠償を求めた事例(R7終了)
-
Case39 役員退職慰労金の支払いを求めた事例
-
Case38 取引先に対する損害賠償請求について合意書を交わした事例
-
Case37 無料求人広告サイトの自動更新による不当な掲載費用の請求を諦めさせた事例
-
Case36 異物混入による製造物責任が問われ、早期に協議で解決した事例
-
Case35 海外法人と人材紹介契約締結のための契約書を作成した事例
-
Case34 ステマ規制についてご助言した事例
-
Case33 工事請負取引基本契約の条項において、天災等の不可抗力による損害を元請負人負担とすることをご提案させていただいた事例
-
Case32 テナントビルの賃貸人に対し、テナントが物件事故による損害賠償を請求した事例
-
Case31 これまで取引をしてきたメーカーの海外子会社と改めて預かり金を預ける内容の契約書を締結するにあたり、審査(リーガルチェック)した事例
-
Case30 ネパール法人との契約書リーガルチェック
-
Case29 売主側として、継続的売買契約の基本契約書及び覚書のリーガルチェックを行った事案
-
Case28 独占販売店として取引を行うために必要となる契約書を作成した事案
-
Case27 元従業員の横領行為につき損害賠償を請求して示談が成立した事例