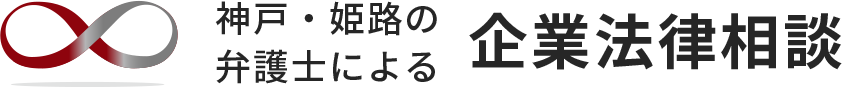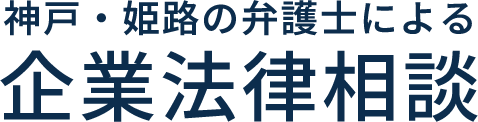景品類の認定と取引付随性
1.はじめに
景品表示法は、「景品類」の提供を規制しています。そのため、景品表示法の規制を受けるか否かを検討するに際しては、「景品類」に該当するかどうかをまず検討する必要があります。
そこで、以下では、「景品類」に該当するかどうかの認定について解説します。
2.「景品類」の定義
景品表示法における「景品類」とは、
①顧客を誘引するための手段として(顧客誘引性)
②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(取引付随性)
③物品、金銭その他の経済上の利益(経済上の利益)
のことを指します。上記①~③の各要件の詳細について解説します。
3.要件①:顧客誘引性
ある物品等の提供が、顧客を誘引する手段として行われたか否かは、客観的に判断されます。つまり、事業者がどういう意図を持っていたかは関係ないということです。
たとえば、図書カードをプレゼントしていたとして、事業者はアンケート調査の回収促進のために行っていたとしても、それが客観的に見て「顧客を誘引する手段だ」と判断された場合には、顧客誘引性が認められてしまいます。
4.要件②:取引付随性
(1)取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合
取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合は、取引付随性ありと判断されます。
〈例〉
・「コーヒー5本買ったら、紅茶1本プレゼント」というキャンペーン
一方、「コーヒー5回飲んだら、コーヒー1杯無料券プレゼント」というキャンペーンは、取引の対象となる商品も、提供される経済上の利益も、同じコーヒーなので、「他の経済上の利益を提供する場合」にはあたらず、景品表示法の規制を受けません。
(2)取引を条件とせずに他の経済上の利益を提供する場合
取引を条件とせずに他の経済上の利益を提供する場合であっても、次の場合には、取引付随性ありと判断されます。
ア 商品の容器包装に経済上の利益を提供する企画の内容を告知している場合
〈例〉
・お菓子のラベルに、「クイズに正解すると抽選で●名様に○○が当たる!」とキャンペーン内容を記載している場合)
イ 商品又は役務を購入することにより、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合
〈例〉
・お菓子の袋を開けたらクイズの答えが書いてある場合
ウ 小売業者又はサービス業者が、自己の店舗への入店者に対し経済上の利益を提供する場合
〈例〉
・「ご来店のお客様に、●●をプレゼント!」というキャンペーン
なお、他の事業者が行う企画であっても、自己が協賛、後援等の協力関係にある場合等はこれに該当するので、注意が必要です。
エ 自己と特定の関連がある小売業者又はサービス業者の店舗への入店者に対し提供する場合
〈例〉
・「当社系列のお店にご来店のお客様に、●●をプレゼント!」というキャンペーン
(3)取引の勧誘に際して金品・招待券等を供与するような場合
取引の勧誘に際して、相手方に、金品・招待券等を供与するような場合は、取引付随性ありと判断されます。
5.要件③:経済上の利益
経済上の利益があるか否かは、提供を受ける側の視点から判断します。
つまり、事業者が、そのための特段の出費を要しないで提供できる物品等であっても、提供を受ける者の側からみて、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものは、「経済上の利益」に含まれます。
また、商品等を通常より安く購入できる利益も、経済上の利益に含まれます。
6.まとめ
このように、一般のイメージよりも「景品類」の範囲は広く、予想外に景品表示法上の景品規制を受ける場合があります。
BtoCビジネスで何らかのキャンペーンを検討中の事業者様は、ぜひ一度、景品表示法に詳しい弁護士にご相談ください。
広告記事
-
広告
Q.企業向けの販売セミナーをしたいと考えています。セミナー参加者全員に,参加特典として自社商品をお渡ししようと思うのですが,問題ないでしょうか。
-
広告
Q.化粧品の広告規制について
-
広告
おとり広告(景品表示法)の法的注意点
-
広告
広告における打消し表示
-
広告
広告における二重価格表示
-
広告
広告における不当表示
-
広告
景品規制における法的留意点
-
広告
景表法における景品類の認定と取引付随性について
-
広告
景表法で規制される「有利誤認表示」とは
-
広告
ステルスマーケティング規制の概要(令和5年10月1日施行)
-
広告
景品表示法における管理措置指針の概要と社内体制整備について
-
広告
No.1表示を行う際の景表法上の留意点
-
広告
令和5年景品表示法改正の概要
-
広告
コンプガチャの禁止とその対策
-
広告
ライブイベントやコンサートの座席に関する不当表示とその予防策